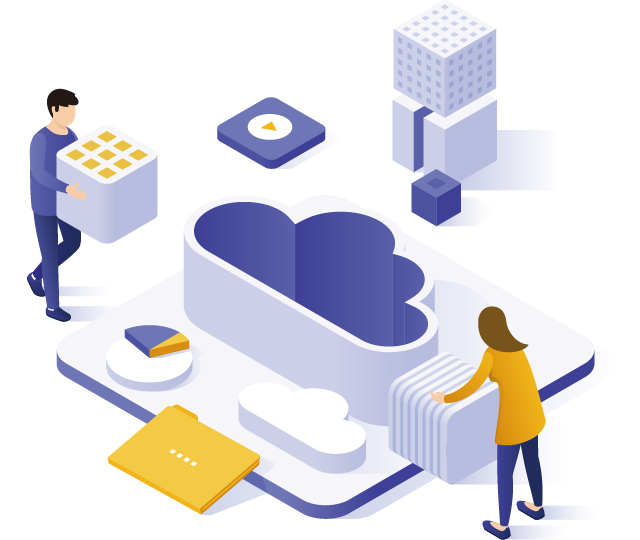ECサイトはセキュリティ対策なしでは危険
~立ち上げ・運営時の対策~
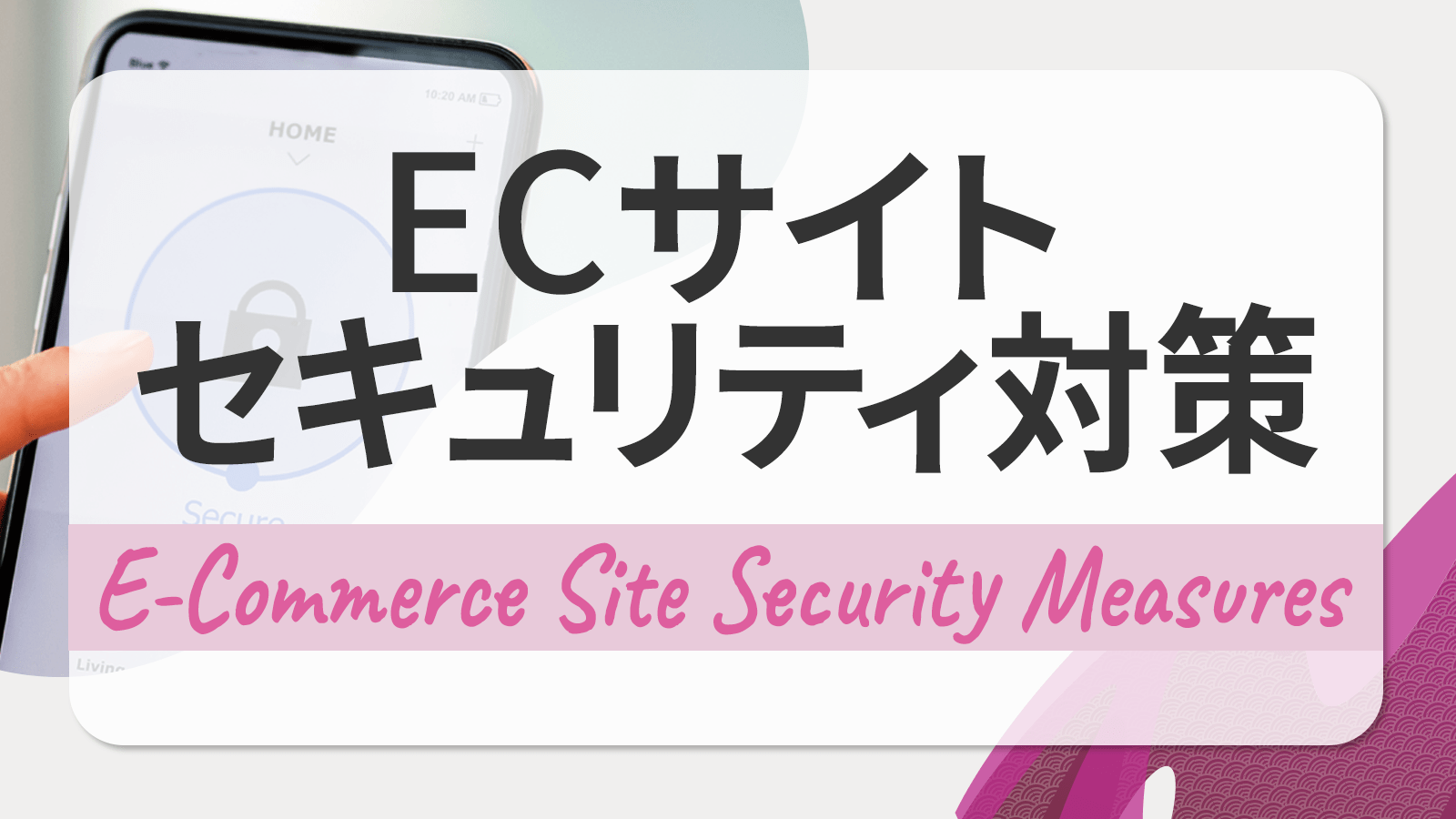
ECサイトを運営する上で情報セキュリティ対策は必要不可欠です。ECサイトでは個人情報や決済データを扱うためサイバー攻撃の標的になりやすく、万が一被害を受けると、顧客の信頼を失うだけでなく、事業の継続が困難になる恐れもあります。
近年、サイバー攻撃の手口は巧妙化しており、従来の対策だけでは十分とは言えないケースが増えています。そのため、ECサイト運営者はセキュリティ意識を高め、定期的な診断や最新の対策を講じることが求められます。
この記事では、EC事業を運営する担当者や責任者に向けて、構築段階と運用段階の双方の観点から、ECサイトに必要なセキュリティ対策について詳しく解説しております。ぜひお役立てください。
1.ECサイトにセキュリティ対策が必要な理由
ECサイトの運営には、万全なセキュリティ対策が不可欠です。ECサイトは常にサイバー攻撃のリスクにさらされており、ひとたび情報漏えいなどのインシデントが発生すると、信用の失墜やサイト閉鎖につながる可能性があります。
ここでは、ECサイトにおけるセキュリティ対策の重要性について、具体的なリスクとともに解説します。
1-1.サイバー攻撃のターゲットになりやすい
ECサイトはクレジットカード情報を含む機密情報や個人情報など、価値の高いデータを扱うため、攻撃者にとって魅力的なターゲットになりやすい特徴があります。
IPA(情報処理推進機構)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2024」によると、ECサイトを狙った「不正アクセス」や「マルウェア攻撃」が引き続き大きな脅威となっています。さらに、フィッシング詐欺やランサムウェアといった新たな攻撃手法も増加傾向にあり、ECサイト運営者はこれらの脅威に対応できるセキュリティ対策を強化する必要があります。
1-2.ECサイト内の情報が漏洩し信用失墜につながる
ECサイトで情報漏えいが発生すると、顧客の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報などが流出するリスクがあります。万が一このような事態が起これば、顧客の信頼は著しく低下し、ブランドの信用回復には多大な時間とコストがかかるでしょう。
また、情報漏えいの発生後には、原因調査や顧客対応に追われるほか、法的な制裁を受ける可能性もあります。個人情報保護法に基づく罰則や、監督官庁からの業務改善命令など、企業経営に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、セキュリティ対策の強化は必須と言えます。
1-3.多額の金銭的損失が発生する
セキュリティ対策を怠ると、情報漏えいによる損害賠償やシステム復旧費用、事業停止に伴う売上損失など、多額のコストが発生する可能性があります。
たとえば、ECサイトがサイバー攻撃を受けた場合、一時的にサイトを閉鎖せざるを得なくなり、その間の売上損失が大きくなることも考えられます。また、事故対応に必要な専門家の手配や、今後のセキュリティ強化に伴う追加コストも発生するため、事前にしっかりと対策を講じることが重要です。
具体的なデータは変動するものの、ECサイトの閉鎖期間における売上高の損失額についてみると、従業員規模300名以下の40社を対象とした場合、1,000万円以上の損失額が26社(対象の65%相当)で発生したとの結果がでています。
【ECサイト閉鎖期間における売上高の損失額】
※従業員規模300名以下の40社を対象
1,000万円未満:14社
1,000万円以上2,000万円未満:12社
2,000万円以上3,000万円未満:5社
3,000万円以上5,000万円未満:2社
5,000万円以上1億円未満:3社
1億円以上:4社
IPAによると、事故対応費用の平均額は約2,400万円にのぼるとされています。この損失は、特に中小企業にとって経営を大きく揺るがす要因となりかねません。
また、情報漏えい事故の影響は長期にわたることが多く、顧客の信頼回復や売上の回復には相当の時間とコストがかかります。さらに、セキュリティ事故後の対策強化にも追加の投資が必要となり、事後の対応コストは事前の対策コストを大きく上回る可能性が高いです。セキュリティ対策への投資は、上記のリスクを回避するための必要不可欠な経費として捉えるべきでしょう。
altcircleのOMO ECプラットフォームでは、常に最新のセキュリティ状態を保持したプラットフォームにより、安全安心のEC運営をご支援します。ぜひご相談ください。
2.ECサイトへのサイバー攻撃の主な手口
サイバー攻撃の手法は年々巧妙化しており、ECサイト運営者は常に最新の脅威に備え、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。ここでは、ECサイトを狙った代表的なサイバー攻撃の手口について解説します。
2-1.SQLインジェクション
SQLインジェクションは、ECサイトのデータベースを不正に操作する攻撃手法です。攻撃者は、ログインフォームや検索ボックスなどの入力欄に不正なSQL文を入力することで、顧客情報を盗み出したり、データを書き換えたりします。
SQLインジェクションの対策方法には、以下が挙げられます。
- 入力データの厳格なチェック
- プレースホルダを用いた安全なSQL実行
- データベースのアクセス権を最小限に制限
入力データの厳格なチェックやプレースホルダの使用、データベースアカウントの権限制限や定期的な脆弱性診断が有効です。Webアプリケーションの設計段階からセキュリティを考慮し、SQLインジェクションのリスクを低減することが求められます。
2-2.クロスサイト・スクリプティング
クロスサイト・スクリプティング(XSS)は、ECサイトのWebページに悪意のあるスクリプトを埋め込み、ユーザーの情報を盗んだり、フィッシング詐欺に誘導したりする手法です。ユーザーに直接的な被害を与えるだけでなく、ECサイトの信頼性を大きく損なうこともあります。
XSSを防ぐ方法には、以下があります。
- HTMLエスケープ処理の徹底
- Content Security Policy(CSP)の適用
- ユーザー入力データの適切なサニタイズ
上記のほか、Webアプリケーションフレームワークのセキュリティ機能を活用した定期的な脆弱性診断の実施も重要です。Webサイトのセキュリティ対策を強化することで、XSSによる被害を防げます。
2-3.OSコマンド・インジェクション
OSコマンド・インジェクションは、Webアプリケーションの脆弱性を突いて、サーバー上で不正なOSコマンドを実行させる攻撃手法です。この攻撃を受けると、サーバー内のデータが改ざん・削除されたり、不正プログラムが実行されたりする恐れがあります。最悪の場合、攻撃者にサーバーの管理権限を奪われ、ECサイト全体が機能しなくなるリスクもあります。
OSコマンド・インジェクションを防ぐ方法は以下の通りです。
- 入力データの厳格なチェック
- OSコマンドの直接実行を回避
- 最小権限の原則を適用
- 定期的な脆弱性診断の実施
適切なセキュリティ対策を講じることで、OSコマンド・インジェクションのリスクを大幅に低減し、安全なECサイト運営が可能になります。
3.サイバー攻撃で被害を受けやすい危険なECサイトの特徴
個人情報保護委員会の「ECサイトへの不正アクセスに関する実態調査」によると、サイバー攻撃の被害を受けやすいECサイトには以下のような共通の特徴があります。
- 脆弱性に対する理解不足:66%
- 委託先任せの姿勢:59%
- セキュリティ対策に関する契約の不備:54%※
- リスク意識の欠如:44%
- 予算や人的リソースの不足:44%
-
「契約書等にセキュリティ対策の記載はあるが具体的ではない」「契約書等にセキュリティ対策の記載がない」の合計)
調査では、セキュリティに関する知識や認識の不足、また委託先に任せきりにしてしまう姿勢が不正アクセスを受ける原因となったことが判明しています。
上記の特徴を持つECサイトは、サイバー攻撃のリスクが高く、情報漏えいなどの被害に遭う可能性が高いため、早急な対策が必要です。
ECサイトの開発を外部委託する場合でも、セキュリティ対策の責任範囲や内容について事前に明確化するのが重要です。また、委託先に丸投げせず、自社内でもセキュリティ人材を育成するか確保して、複数のセキュリティ対策を組み合わせた防御を行いましょう。
altcircleのOMO ECプラットフォームは、常に最新のセキュリティ状態を保持します。不正アクセスへの対策が足りていないとお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
4.ECサイトが構築時に行うべきセキュリティ対策
ECサイトを安全に運用するためには、開発段階からセキュリティを考慮する必要があります。ここでは、サイト構築時に取り組むべき具体的なセキュリティ対策について解説します。
4-1.セキュリティ対策の方針策定および予算・体制の準備
セキュリティ対策は、単発の対応ではなく、継続的な取り組みが求められます。そのため、組織全体で明確な方針を定め、必要な予算や人員を確保することが重要です。
具体的な施策例としては、以下が挙げられます。
- ECサイトにおけるセキュリティリスクを分析し、適切な対策計画を策定
- 必要な予算を確保し、最新のセキュリティ技術や診断ツールを導入
- 専門的な知識を持つ担当者を配置し、定期的な研修や教育を実施
外部事業者に委託する場合は、委託先の選定基準を明確にし、セキュリティ対策に関する実績やノウハウを持つ事業者を選びます。委託契約書には、セキュリティ対策の具体的な内容、責任範囲、情報漏えい時の対応などを明記し、定期的な監査を実施することが重要です。どのような体制が必要かについては、経済産業省が公開している「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」なども参考にしましょう。
4-2.IPAのガイドラインに準拠したECサイトの構築
IPA(情報処理推進機構)では、Webセキュリティのガイドラインを公開しており、ECサイト構築時の指針として活用できます。特に重要な対策項目は、以下の通りです。
- SQLインジェクションやXSS(クロスサイト・スクリプティング)対策の徹底
- アクセス権限の適切な設定(管理者権限の最小化)
- 不正ログイン防止のための多要素認証導入
IPAのガイドラインには、SQLインジェクションやXSSなどの代表的な脆弱性に対する対策、認証・認可の強化、入力データの検証、エラー処理の適切な実装などが含まれています。この対策をECサイトの設計・開発段階から組み込むことで、脆弱性を抱えたECサイトを公開するリスクを低減できるでしょう。
4-3.ECサイト公開前の脆弱性診断
ECサイトを公開する前に、セキュリティホールを検出し、問題を修正することが不可欠です。専門の脆弱性診断ツールを活用し、事前にリスクを洗い出すことで、攻撃の機会を減らせます。以下をポイントに診断を実施しましょう。
- フォームや入力欄のSQLインジェクション耐性チェック
- ユーザー認証の脆弱性評価
- アクセス制御やセッション管理の適切性確認
脆弱性診断では、SQLインジェクション、XSS、OSコマンド・インジェクションなどの脆弱性の有無をチェックします。また、設定ミスや古いバージョンのソフトウェアの使用など、セキュリティ上の問題点も発見できます。診断で発見された脆弱性は、早急に修正し、安全な状態でサイトを公開しましょう。
4-4.二要素認証の導入
二要素認証は、ID・パスワードに加えて、別の認証手段を取り入れることで、セキュリティを強化する仕組みです。代表的な認証方法には以下があります。
- SMSやアプリを使ったワンタイムパスワード(OTP)
- 生体認証(指紋・顔認証)
ECサイトに二要素認証を導入すれば、IDとパスワードが盗まれた場合でも、不正ログイン対策として機能し、不正アクセスを防げます。特に、管理者アカウントや決済システムにアクセスするアカウントには、二要素認証を必須化することを推奨します。
4-5.SSL/TLSの利用
ECサイトでは、ユーザーが入力する個人情報やクレジットカード情報を守るために、SSL/TLSによる暗号化通信を必ず導入しましょう。SSL/TLSとは、インターネット上でデータを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSを導入するメリットとしては、以下が挙げられます。
- データの盗聴や改ざんを防止
- 「https://」の表示でサイトの安全性をアピール
- SEO(検索エンジン最適化)の向上
SSL/TLS証明書には、無料のものから有料のものまでさまざまな種類があります。ECサイトの規模やセキュリティ要件に応じて、適切な証明書を選択することが重要です。また、SSL証明書は定期的に更新し、最新の暗号化方式を適用することが大切です。
4-6.クレジットカードの不正防止対策
ECサイトでの決済において、不正利用を防ぐための対策が必要です。特に、クレジットカード決済におけるセキュリティ対策を強化する必要があります。
クレジットカードの不正利用を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- 3Dセキュアの導入
- セキュリティコードの入力
- 不正検知システムの導入
- クレジットカード情報の非保持化
経済産業省もクレジットカード不正利用対策の重要性を啓発しており、ECサイト運営者は上記の対策を参考に、自社のECサイトに適した不正防止対策を講じることが重要です。
5.ECサイトの運営にあたって行うべきセキュリティ対策
ECサイトは、構築時だけでなく、運営段階においても継続的なセキュリティ対策が不可欠です。サイバー攻撃の手法は日々進化しており、一度安全を確保したからといって安心はできません。ここでは、ECサイトの運営において常に意識すべきセキュリティ対策について解説します。
5-1.最新のソフトウェアの利用
ECサイトの安全性を維持するために、使用しているソフトウェアを最新バージョンへ定期的に更新することが重要です。ここでいうソフトウェアには、OS、Webサーバー、CMS、ECプラットフォーム、プラグインなどが含まれます。
更新を怠ると、以下のリスクが発生します。
- 既知の脆弱性が残り、サイバー攻撃の標的になりやすくなる
- 不正アクセスや情報漏えいのリスクが高まる
- サイト改ざんやマルウェア感染の被害を受ける可能性がある
各ソフトウェアの開発元は、セキュリティの脆弱性を修正するためのアップデートを定期的に公開しています。そのため、リリースされた更新プログラムは、速やかに適用することが必須です。
5-2.定期的な脆弱性診断や改ざん検知ツールによる監視
ECサイトを安全に運営するためには、定期的な脆弱性診断を実施し、システムのセキュリティホールを特定・修正することが重要です。特に、サイトの規模が大きくなるにつれて、潜在的なリスクも増加するため、継続的な診断が求められます。
また、サイト改ざん検知ツールを導入することで、サイト内の不正な変更をリアルタイムで監視でき、万が一攻撃を受けた場合でも迅速な対応が可能です。推奨される対策として以下があります。
- 定期的な脆弱性スキャンを実施(少なくとも四半期ごと)
- 改ざん検知ツールの導入(Webページの改変を即座に検知)
- アクセスログを分析し、不審な動きをチェック
セキュリティリスクを最小限に抑えるために、IPA(情報処理推進機構)のガイドラインも参考にしながら対策を進めるとよいでしょう。
5-3.定期的なバックアップ・ログの取得とチェック
サイバー攻撃やシステム障害が発生した際に、被害を最小限に抑えるためには定期的なバックアップが不可欠です。バックアップのポイントには、以下が挙げられます。
- データベース、サイトファイル、設定情報などを対象に、複数のバックアップを取得
- 別のサーバーやクラウドにバックアップを保管し、物理的なリスクにも対応
- バックアップデータの定期的な復旧テストを実施し、正常に復元できるか確認
また、アクセスログや操作ログを取得・分析することで、不審なアクティビティを早期に検出し、攻撃の兆候を察知することが可能になります。
5-4.WAFの導入
WAFとは、Web Application Firewallの頭文字を取った略称で、ECサイトに対する攻撃をリアルタイムで検知し、不正なアクセスをブロックする防御システムです。WAFを導入するメリットには、以下があります。
- SQLインジェクション、XSS(クロスサイト・スクリプティング)などの攻撃を防止
- サーバーへの不正アクセスをブロックし、データの改ざんを防ぐ
- ECサイトの脆弱性が修正されるまでの「暫定的な防御策」としても機能
WAFには、大きく分けて以下の3種類があり、ECサイトの規模やセキュリティ要件に応じて適切なタイプを選択する必要があります。
- ソフトウェア型WAF:比較的安価で導入しやすい
- ハードウェア型WAF:より強力な防御機能を備え、大規模サイト向け
- クラウド型WAF:導入が簡単で、継続的なメンテナンスが不要
WAFの設定や運用には専門的な知識が必要となるため、外部の専門業者と連携して適切な設定を行うことを推奨します。
5-5.サイバー保険への加入
ECサイトに対するサイバー攻撃のリスクを考慮すると、サイバー保険に加入することで、万が一の際の損害をカバーできる可能性があります。サイバー保険の主な保証範囲は、以下の通りです。
- 情報漏えいに伴う損害賠償金の補填
- システム復旧費用の補償(攻撃によるECサイトのダウンタイム対応)
- 事業停止に伴う売上損失のカバー
- 法的対応(弁護士費用など)の補償
サイバー保険を選ぶ際は、ECサイトの規模や取り扱うデータ量に適した補償内容を選択することがポイントになります。DDos攻撃やランサムウェアなどの被害も補償の対象になるかなど、補償対象となるリスクの範囲を確認しましょう。複数の保険会社を比較し、最適なプランを選定することも大切です。
ただし、サイバー保険はあくまで「最後のリスク対策」であり、基本的なセキュリティ対策の徹底が最優先です。
6.まとめ
ECサイトのセキュリティ対策は、構築時だけでなく、運営段階においても継続的に取り組むべき重要な課題です。サイバー攻撃の手口は日々巧妙化しており、一度対策を講じたからといって安心はできません。常に最新の脅威を把握し、適切な対策を講じ続ける必要があります。特に、セキュリティパッチの適用を怠ると、脆弱性を悪用されるリスクが高まります。
セキュリティ対策に不安を感じている、ECサイトの運営効率化や売上拡大に悩んでいるといった場合は、ぜひaltcircleのOMO ECプラットフォームをご検討ください。altcircleのOMO ECプラットフォームは、常に最新のセキュリティ状態を保持し、安全安心のEC運営をご支援します。また、顧客接点の高度化、コスト最適化、EC運用効率化など、ECビジネスにおけるさまざまな課題解決をサポートします。お気軽にご相談ください。