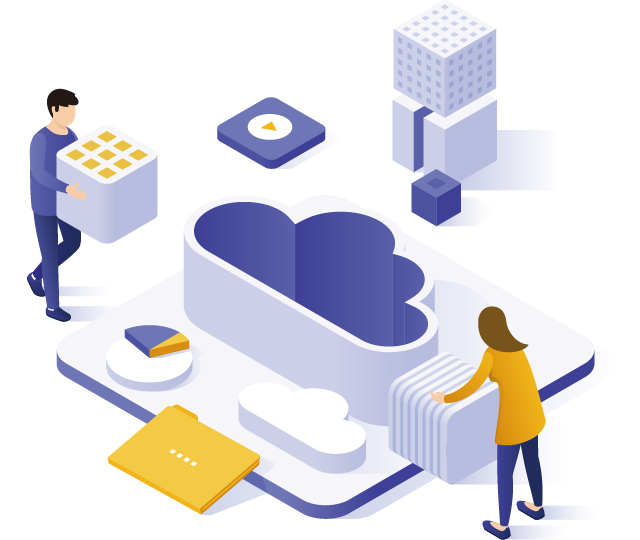BtoB-EC(B2B-EC)とは?
基礎知識やメリット・事例を解説!
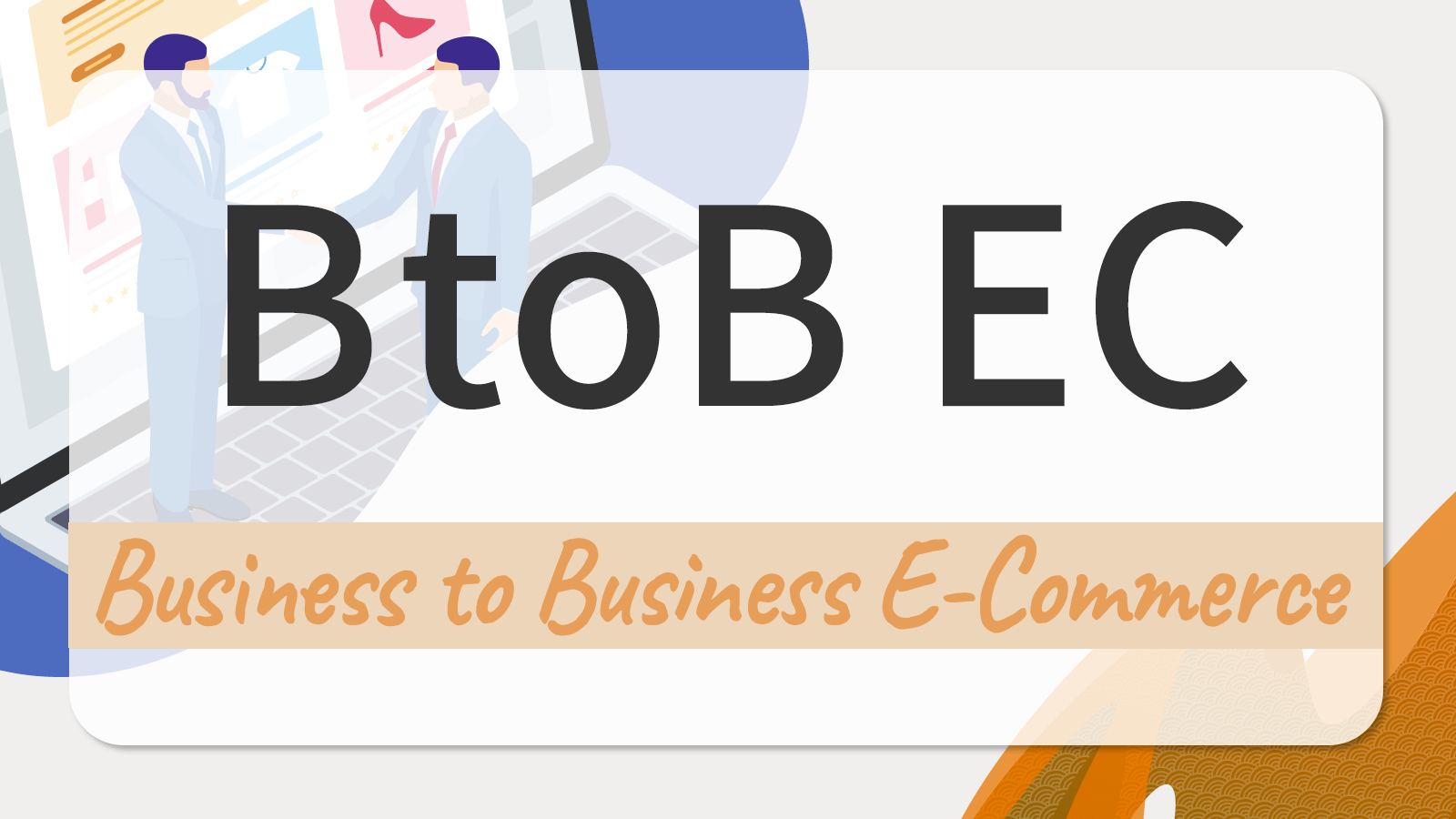
ECは一般消費者向けのサービスと考える方も多くいますが、近年では企業間取引を指す「BtoB(B2B)」のビジネスにおいても導入が進んでいます。
BtoB-EC(B2B-EC)の導入には、受発注業務の効率化をはじめとしたさまざまなメリットが期待でき、大手企業による成功事例も存在します。一方でデメリットもあり、自社の課題や業務を踏まえて、適合したタイプを選定しなければメリットを享受できない可能性がある点に注意が必要です。
この記事では、BtoB-ECの導入を検討している方へ向けて、BtoB-ECの概要やBtoB-EC市場が拡大している理由、さらに導入によるメリット・デメリットや機能、成功事例について解説しております。ぜひお役立てください。
1.BtoB-EC(B2B-EC)とは?
BtoB-EC(B2B-EC)とは、名前の通り「BtoB」と「EC」を組み合わせた造語で、ECサイトを通して企業間取引を行うことや、その仕組み・システムのことです。なお、広義にはEDIも含む企業間のオンライン取引全般を指しますが、この記事ではより狭義の「ECサイトを通したBtoB取引」を「BtoB-EC」と定義しています。
そもそもBtoBとは、企業間取引を意味する「Business to Business」を簡略化した言葉で、「B2B」とも表記されます。そして、ECは電子商取引を意味する「Electronic Commerce」の頭文字をとった略称で、インターネット上で商品やサービスを売買することを指し、「Eコマース(イーコマース)」とも呼ばれます。
ネットショップや通販サイトとも呼ばれるECサイトは、かつて一般消費者をターゲットにしたものが中心でした。しかし、近年ではBtoBの企業間取引においても、受発注業務の効率化や販路の拡大を目的にBtoB-ECを導入する企業が増えています。
BtoB-ECは、通常のECサイト同様にWebページ経由で受発注を行えるため、これまで企業間取引に使われてきたEDIと比べ、専用回線を用意する必要がありません。受発注業務もデジタル化によってスムーズになるため、BtoBにおいてもECサイトの導入には多くのメリットが存在します。
altcircleでは、BtoB ECの活用で業務効率化を実現するユースケースについて以下で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
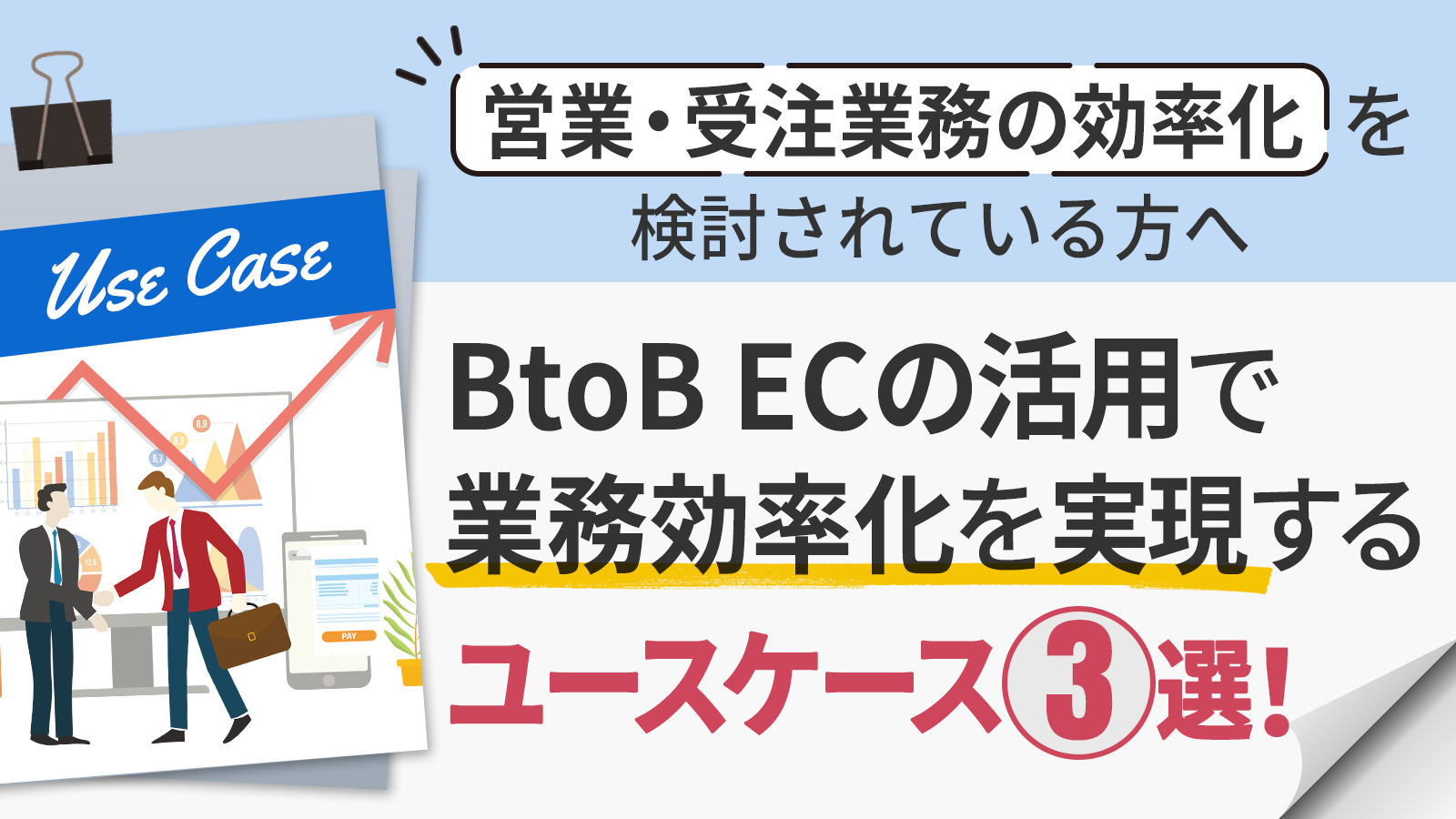
1-1.BtoB-ECとBtoC-ECの違い
BtoB-ECとBtoC-ECは、いずれもECサイトを通して取引を行う点は共通しているものの、電子商取引の相手に大きな違いがあります。
そもそもBtoC-ECの「BtoC」とは、「Business to Consumer」の略称で、企業が一般消費者向けに取引を行うビジネスモデルのことです。したがって、取引対象が企業となるBtoB-ECとは違って、BtoC-ECは一般消費者が取引対象となります。
このように、BtoB-ECとBtoC-ECとでは取引のターゲットが異なることから、特徴やECサイトに求められる機能も異なる点を覚えておきましょう。
たとえば、取引対象が一般消費者となるBtoC-ECは基本的に商品価格をオープンにして、どのユーザーに対しても同価格で商品を販売しています。
一方で、BtoBでは取引先ごとに価格設定や決済方法が異なるケースも多々あることから、BtoB-ECにおいては会員(取引先)ごとに表示する価格を変更する機能が必要な場合が多いです。
1-2.BtoB-ECとEDIの違い
EDIとは、「Electronic Data Interchange」の頭文字をとった略称で、「電子情報の交換」を意味します。取引で発生したメッセージや帳票をインターネット上でやり取りするシステムで、「従来の紙のやり取りを電子化する」ことを目的としています。
EDIは、企業間取引で長く主流となっていたシステムです。通常、ISDN回線などを用いて、他社から受け取ったデータを自社で読み取り可能な形へと変換します。そのため、売り手は買い手側の規格に合わせて、変換可能な形にEDIを選ぶことが主流でした。
しかし、2024年にNTTがISDN回線の提供を終了し、IP網への完全移行を発表したことで「EDIの2024年問題」が生じました。これに伴い、Web-EDIへの移行が進められていますが、データ形式や取引画面の仕様が標準化されていないことから「多画面化」と呼ばれる課題も発生している状況です。
そのため、最近ではEDIの根本的な課題を解決する手段として、インターネットを活用したBtoB-ECの開発・導入を選ぶ企業が増えています。
BtoB-ECはパソコンやスマートフォン(スマホ)などのデバイスとインターネット回線があれば取引を行えるため、売り手が買い手に合わせてEDIを導入する必要がありません。
2.BtoB-ECの市場規模
BtoB-EC市場は2023年時点で「465兆2,372億円」に達し、前年比10.7%増という高い成長率を記録しました。ただし、経産省の定義においては、BtoB-EC市場にはEDIも含まれているため、このコラムの定義であるより狭義のBtoB-ECの市場規模を正しく表した指標ではありません。
しかし、近年の企業間取引におけるオンライン化の急速な進行が反映されていると言え、BtoB-EC市場は高成長していると言えるでしょう。
企業間取引の業務効率化やコストの削減を実現する手段としてますます注目を集めており、今後もBtoB-ECの持続的な拡大が見込まれています。
2-1.BtoB-ECの市場規模が拡大している理由
BtoB-EC市場が拡大している理由としては、下記が考えられます。
働き方改革によるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進
働き方改革によってDX推進が求められる近年、BtoB-ECは受発注業務の効率化やペーパーレス化を目指す取り組みの一環として導入が進んでいます。
BCP(事業継続計画)の重要性の高まり
オンライン取引は、万が一自然災害やパンデミックによる被害が発生しても事業継続性を確保できる手段として注目されています。その中でもBtoB-ECは、物理的な制約を受けにくい取引形態であることから、BCP対策の一環として多くの企業に選ばれています。
ITインフラやスマートフォン・タブレット(スマートデバイス)の普及
デジタル技術の成長によってITインフラの整備とスマートデバイスの普及が進んだ近年、商取引においても場所や時間に縛られない環境が整いました。これにより、BtoB-ECの利便性も大きく向上し、多くの企業が導入に踏み切っています。
3.BtoB-ECを導入するメリット
BtoB-ECを導入することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。
ここからは、それぞれのメリットについて解説します。BtoB-ECの導入を検討している担当者の方は、ぜひお役立てください。
3-1.受注業務のミスや工数を減らせる
従来のアナログな取引では、データの入力・確認や見積もりの作成といった基幹業務を手作業で行う必要があり、人為的ミスの発生や業務負担の増大が避けられませんでした。また、基本的には受発注手続きは営業時間内でしか対応できないため、競合の多い市場では受注機会を逃す要因にもなっていました。
しかし、BtoB-ECを導入することで、これらの受注業務をすべてデジタル化・自動化できます。煩雑な手作業を削減し受注業務の効率化を実現できるだけでなく、人為的なミスの防止や受注機会の拡大にもつながるでしょう。
3-2.新規顧客・既存顧客の双方への接点になる
従来のBtoB取引においては、担当者が取引先に直接出向いて交渉するのが一般的でした。しかし、営業所のないエリアや遠方の顧客へのアプローチは距離やリソースの問題から簡単とは言えず、近年ではリモートワークの普及によって対面での交渉がますます難しくなっています。また、営業担当者のリソースは限られているため、大口顧客に対してリソースを割く一方で、小口顧客へアプローチする優先度を落とすケースが多いでしょう。
一方で、BtoB-ECは24時間365日利用できるオンライン窓口として機能するため、すべての顧客に「気軽にアクセスできる環境」「追加注文・再注文をスムーズに行える利便性」を提供できます。
場所に縛られない取引を可能とすることで、従来ではアプローチしきれなかった幅広い顧客との接点をもつことができ、結果として販売促進や新規顧客の獲得に寄与します。小口顧客にも訴求でき、これまで営業担当者が取りこぼしていた顧客の獲得にもつながるでしょう。
3-3.顧客の購買行動や市場動向をデータで把握しやすい
BtoB-ECでは、顧客の閲覧履歴や注文履歴のほか、売上・販売数やリピート率といった取引データが自動的に蓄積されます。これらのデータを分析することで、購買行動の傾向や市場の動向を把握しやすくなります。
また、分析結果をもとに、顧客に適したクロスセルの提案や効果的なマーケティング施策を展開することで、売上アップが期待できるでしょう。
3-4.顧客体験の向上につながる
従来のアナログ取引をデジタル化し、ECによるスムーズな取引環境を提供することは、顧客にとっても多くのメリットがあります。
BtoB-ECはインターネット環境があれば場所や時間を問わず、商品の詳細情報や在庫状況、納期を簡単に確認でき、手軽に発注できます。注文プロセスがシンプルで便利になるため、受注側だけでなく発注側となる顧客にとっても業務負担の軽減が実現し、顧客体験の向上にもつながります。
結果として、顧客との関係が一層深まり、長期的な取引の促進にもつながります。売り手にとっても新規顧客の獲得やリピート購入の増加といったメリットが得られるでしょう。
4.BtoB-ECを導入するデメリット
BtoB-ECの導入は企業に多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在することに注意が必要です。導入後の後悔を防ぐためにも、あらかじめデメリットも把握しておきましょう。ここからは、BtoB-ECを導入する主なデメリットを3つ説明します。
4-1.導入にコストがかかる
BtoB-ECサイトは、業界・企業ごとの商慣習や取引形態を加味して個別にカスタマイズされた独自のシステムを構築する必要があり、一般的なBtoC-ECサイトに比べて制作・構築に多額のコストがかかります。
ECサイトの規模や求めるデザイン、基幹システムとの連携など、構築方法によっては導入のコストが数千万円に達するケースもあるでしょう。
4-2.既存顧客へのフォローが必要になる
電話やFAX、メールなどによる従来の発注手段に慣れ親しんでいる既存顧客の場合、BtoB-ECサイトを経由する新たな発注方法への大幅な変更に抵抗感を示す可能性もあります。特に、「ECサイトが非常に使いづらい」と感じられた場合は取引中止に至るおそれがある点にも注意が必要です。
そのため、従来の発注手段に慣れている既存顧客には、事前にECサイトでの発注方法に関するマニュアルを提供したり、デモサイトを活用して操作方法を説明したりするなど、丁寧なフォローが不可欠となります。
4-3.社内の業務フローの変更が求められる
BtoB-ECシステムの導入には、社内の業務フローの見直しも伴います。導入後はすぐに運用が定着するわけではなく、関係部署との調整と連携が必要です。
この調整段階で新たな課題が見つかったり、従来の業務プロセスを変更することに対する反発が生じたりする可能性もあるでしょう。また、システムの理解が十分でない担当者や経験の浅い担当者が不適切な操作を行うことで、データ破損や情報漏洩といったセキュリティリスクが発生する可能性も否めません。
業務フローの見直しや運用の定着をできる限りスムーズに進めるためには、新システムの導入に向けた社員教育を実施したり、社内向けの操作マニュアルを作成したりして、関係者としっかり共有することが不可欠です。
5.BtoB-ECの種類
BtoB-EC向けのサイトには、大きく分けて「オープン型(スモール型)」と「クローズド型」の2種類があります。
オープン型(スモール型)
一般的なBtoC向けのECサイトと同様に、インターネット上で会員・顧客を問わず誰でも商品情報を閲覧できるタイプのBtoB-ECサイトです。商品を広い範囲のターゲット層に公開でき、認知度の向上・市場進出のスピードアップが見込めます。
一方で、商品情報や価格が公開されるため、情報管理・価格競争において課題が生じる可能性があるほか、ターゲット層が広いことから販促活動の工夫が求められます。
オープン型BtoB-ECは新規顧客の獲得や売上向上に効果的であり、営業担当者がアプローチできない遠方の取引先や小口取引の顧客との取引に適しています。
クローズド型
サイトURLを共有された特定のユーザーだけが閲覧できるタイプのBtoB-ECサイトです。基本的に、ID・パスワードでログインした会員のみがサイトを利用できるよう、アクセス制限がかけられています。
取引先企業の担当者以外はサイト内を確認できないため、商品情報や価格の機密性が保たれるほか、顧客ごとに価格設定をカスタマイズすることも可能です。一定量の取引がある企業間では効率化が図れる一方で、新規顧客の獲得においてはオープン型に劣る場合があります。
クローズド型BtoB-ECは、既存顧客との関係やリピート営業を強化したい場合に適しています。
5-1.BtoB-ECに必要な機能
BtoB-ECは、一般的なBtoC-ECと比較して異なる機能が求められる点が特徴です。BtoB-ECに必要とされる主な機能について紹介します。
顧客管理機能
顧客となる取引先の企業情報や取引条件、さらに販売対象商品や取引履歴を管理できる機能です。
見積もり作成・管理機能
注文内容に応じた見積書を自動で作成・表示したり、作成した見積書を有効期限ごとに保存・管理したりする機能です。
価格・掛け率管理機能
商品の販売価格や掛け率を取引先や商品カテゴリごとに設定できる機能です。
承認機能
取引先企業内の複数担当者による発注承認フローを電子化して組み込める機能です。あらかじめ定めた承認プロセスを踏むまでは、注文処理が行われません。
決済管理機能
銀行振込やクレジットカード決済、掛け売りなどのあらゆる決済方法に対応したり、取引先ごとの決済条件や与信限度額を管理したりする機能です。
6.BtoB-ECの成功事例
多くの企業がBtoB-ECの導入を進めている近年、成功を収めた事例も数多く報告されています。最後に、BtoB-ECの活用によって、以下のような成果を上げた4つの企業の事例を紹介します。
BtoB-ECの活用がもたらした4つの成果
- 顧客体験の向上
- 顧客接点の増加
- 販売件数の増加
- 業務の効率化
6-1.モノタロウ
モノタロウは、建設業や製造業の現場で必要な工具や資材、備品などを販売するオープン型BtoB-ECです。2001年に運営を開始し、2013年には大企業向けサービスも展開するなど、業界最大級の品揃えを誇る老舗の事業者向けECサイトとして知られています。
モノタロウの最大の強みは、必要な商品を素早く見つけられる充実した検索機能です。取扱商品は2024年時点で2,300万点を超えているものの、商品は詳細にカテゴライズされているほか、カタログに記載された注文コードを入力するだけで目的の商品を簡単に見つけられます。
また、1点から注文できるシステムによって、小口発注を希望する中小企業にも幅広く利用されています。2024年度の売上高は約20兆2,635億円と報告されており、前年比13%増という高成長を遂げている企業です。
6-2.アスクル
アスクルは、文具や事務用品、パソコン周辺機器などのオフィス用品を中心に販売するオープン型BtoB-ECサイトです。法人向けに最適化されたサービスも提供しており、割引価格や大口注文、さらに請求書払いなどの多様な支払い方法に対応しています。
また、アスクルでは顧客開拓や債権回収は独自の代理店に依頼し、注文・発送は自社で行うという効率的な体制を採用し、スムーズな取引を実現していることも特徴です。さらに、顧客の多い地域を中心に物流センターを配置し、都市部では当日配送にも対応するなど、迅速なサービスの提供を心がけています。
2023年6月から2024年5月までの年間売上高は4,716億円と報告されており、直近10年間はすべて右肩上がりを維持しています。
6-3.ミスミ
ミスミは、金型部品やFA機器、工具・消耗品などを販売するオープン型BtoB-ECサイトです。自社製品のみならず多数のメーカー品を取り扱っており、商品数は3,000万点、そのバリエーションは800垓(1兆の800億倍)にも及びます。
2022年10月末にはECサイトをリニューアルし、膨大な商品ラインナップの中から目的の商品を簡単かつ的確に選べる仕組みを構築しました。また、最短当日出荷にも対応しており、顧客の時間価値の向上に注力しています。
さらに、2024年6月末にはGoogleが提供するベクトル検索実行サービス「Vertex AI Vector Search」を導入しました。商品の探索時間を18%短縮したことが報告されており、利便性向上への取り組みがより評価されています。
6-4.M社(製造業向けの素材専門商社)
製造業向けの素材を扱う商社であるM社では、長年電話・FAXを用いた受注体制を継続してきました。しかし、業務多様化や需要増加によりオペレーターの負荷が高まってしまったため、クローズドなBtoB-ECサイトを構築し、業務の効率化を実現しました。
新しい仕組みを取引先に利用してもらうための工夫として、「注文と同時にリアルタイムで在庫数を反映」「お届け日数の可視化」「電話・FAXとECサイトを併用できる環境整備」といった機能を用意しました。また同時に、日本全国の顧客を直接訪問して導入の意図や操作方法を説明し、定着を図りました。
結果として、オペレーターの負荷を軽くしつつ営業時間外の注文対応が可能となり、顧客満足度もアップ、競合他社との差別化に成功しています。
7.まとめ
BtoB-ECとは、ECサイトを通して企業間取引を行うことや、その仕組み・システムを指します。DX推進やBCP対策の重要性が高まる近年、BtoB-ECはますます注目されており、導入企業も年々増加しています。
altcircle(オルトサークル)では、企業間取引を支援するBtoB-ECの導入から運用までの包括的なサポートを提供しております。ECサイトの構築はもちろん、効果的なデータ活用や顧客体験向上に向けた施策提案を通じてビジネス成長を後押しします。altcircleのBtoB向けデジタルコミュニケーションプラットフォームサービスについては以下で紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。